- 外国人・グローバル人材
- 公開日:
外国人雇用でよく発生する労働トラブルは?
企業が取り組むべき予防や解決策について

労働力人口の減少や人手不足により、企業において、外国人材の需要は高まり続けています。 採用段階、契約期間中、契約終了段階に分けて、外国人雇用にあたり発生しやすい労働トラブルを紹介した上で、社員が生き生きと働き、企業が発展していくために、企業が取り組むべき労働トラブルの予防策や解決方法について説明します。
まずはお問い合わせください!
LEC東京リーガルマインドは貴社の人材育成を成功させるため、集合研修・eラーニング研修・試験対策研修・ブレンディング研修まで、様々なプランをご用意しております。詳細資料のご請求やお見積りのご依頼は、お気軽に法人事業本部まで。
1.外国人雇用における労働トラブルの全体像と背景
外国人労働者を雇用するにあたり、日本人労働者との以下の違いから、労働トラブルが発生しやすくなっています。
- ①日本語能力の問題から、コミュニケーション不足や行き違いが生じやすいこと。
- ②母国の文化的背景から、仕事に対する考え方や、職場での振る舞いに違いが生じやすいこと。
- ③多くの外国人は、就労の前提として、在留資格の有無や内容が問題になること。
労働施策総合推進法に基づき、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(以下「外国人雇用管理指針」といいます)は、事業主が遵守すべき法令や、努めるべき雇用管理の内容等を列挙しています。 この指針に法的拘束力はないものの、同指針から大きく外れている場合には、将来的に問題が顕在化するおそれがあります。外国人労働者との労働トラブルを防ぐためには、適宜、同指針を参照しながら雇用管理を行う必要があります。
2.採用段階の労働トラブル
外国人労働者を募集し、労働契約を締結するにあたり、賃金、労働時間等の主要な労働条件について、書面で明示することが必要です。労働条件の明示義務は日本人労働者の場合も同様ですが、外国人労働者の場合、 国語や平易な日本語により、十分に理解できる方法で明示するよう努める必要があります(外国人雇用管理指針)。
企業と外国人労働者との間で、労働条件の認識が違っている場合や、外国人労働者が労働条件を正確に理解できていない場合、勤務開始後に外国人労働者から不満が出て、労働トラブルにつながります。
例えば、外国人労働者が日本の源泉徴収について理解していないため、「手取りの賃金が少ない」と不満を持つことがあります。源泉徴収の仕組みや手取り賃金について、丁寧な説明が必要です。 残業の有無や、残業代の計算方法についても、誤解がないように、わかりやすく説明しておくべきです。
働くために外国から日本に来てもらう場合、就労準備費用が高額になるので、その負担をめぐって、外国人労働者との間で裁判になることもあります。外国人雇用管理指針は、
事業主による渡航又は帰国に要する旅費その他の費用の負担の有無や負担割合、住居の確保等の募集条件の詳細について、あらかじめ明確にするよう努めることを求めています。
採用段階で、特に、注意が必要なのは、在留資格に関するトラブルです。
外国人雇用管理主任者認定講座資料を無料でダウンロード頂けます。
外国人雇用管理主任者認定講習の動画一部が無料で視聴いただけます。
LECがおすすめする外国人人材育成/グローバル人材育成研修全体を見る
在留資格について
外国人労働者による就労の可否および就労が認められる範囲は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます)によって定められています。
例えば、専門的・技術的な仕事は「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格が、現業系の仕事は「特定技能」などの在留資格が必要ですが、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の外国人労働者に現業系の仕事をさせることはできません。
また、在留期限の更新をせず期限切れになっている場合も、外国人労働者を働かせることはできません。
「留学」「家族滞在」等の在留資格の外国人が、現に有する在留資格に属さない収入を伴う活動をする場合に資格外活動の許可が必要になりますが、資格外活動の許可の範囲を超えて働かせることはできません。
外国人を不法就労させてしまうと、事業主は、入管法73条の2により3年以下の拘禁刑(※2025年6月1日から懲役刑は拘禁刑に改められます)もしくは300万円以下の罰金に処せられまたはこれを併科されてしまいます。
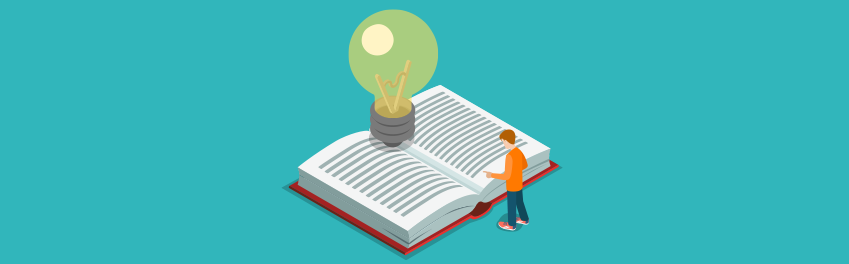
3.契約期間中の労働トラブル
企業は、外国人労働者を含む労働者が、その生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務を負っています(労働契約法5条)。
外国人労働者が、安全衛生教育の理解が不十分なまま危険な作業に従事したり、取扱方法を十分に理解しないまま機械を操作すると、重大な労災事故につながる危険性があります。
また、日本人労働者の場合と同様に、過重労働やハラスメントによって、メンタル不調の問題が生じることもあります。
賃金・労働時間について
労働基準法や雇用保険法等の労働関係法令および社会保険関係法令は、日本人労働者と同様に、外国人労働者にも適用されます。また、賃金、労働時間等の労働条件について、国籍を理由として差別的取扱いをすることは禁止されています(労働基準法3条)。
そのため、外国人労働者への賃金の支払い、労働時間管理等については、日本人労働者と同様に、労働基準法、最低賃金法等に従って適切に対応する必要があります。
外国人労働者のみ、最低賃金法を下回る時給を設定したり、社会保険関係の適用除外にすることは違法です。
ハラスメントについて
職場におけるパワーハラスメント(職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されること)の被害相談は、増え続けています。
外国人労働者との関係では、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント等に加えて、レイシャルハラスメント(人種、国籍、民族文化、宗教的信条などに配慮を欠いた言動)を防ぐ必要があります。
例えば、外国人労働者の母国やその文化を侮辱する発言です。
外国人労働者は、その国籍又は民族的出自に基づいて差別されたり、侮辱されたりしないという人格的利益を有しています。この人格的利益は、あらゆる法律関係において保護されるべき利益です。
企業は、自ら職場において外国人労働者の民族的出自等に関わる差別的思想を醸成する行為をした場合はもちろん、現に職場において差別的思想が醸成されているのにもかかわらずこれを是正せず、放置した場合には、不法行為責任又は債務不履行責任を負います。
外国人雇用管理指針においても、企業は、日本人労働者と外国人労働者とが、文化、慣習等の多様性を理解しつつ共に就労できるよう努めることが求められています。
企業が、人種差別や民族差別を内容とする政治的見解が記載された資料を職場で大量に配布した事案がありましたが、裁判で、外国人労働者の人格的利益が侵害されたとして、外国人労働者に対する損害賠償請求が認められました。
ハラスメントにあたらなくても、チームワークや個人の責任といった働き方に関する考え方の違いから、日本人労働者と外国人労働者との間で関係性が悪化する場合があります。例えば、会社全体の1日の業務が終わらなかった場合に社員が一緒に残業する習慣の企業において、 日本人労働者は他の社員のために残業しているのに、外国人労働者によっては、自分の仕事が終われば帰宅することが当然と考えて、残業をしないで帰宅してしまう場合です。
eラーニング「【外国人向け】日本で働くためのビジネス基礎研修(日本語/ベトナム語)」の一部を無料でお試しいただけます。
4.契約終了段階の労働トラブル
多くの企業では、正社員を採用するにあたり、入社後の一定期間を試用期間とし、この期間中に正社員としての適格性を評価し、本採用とするか否かを判断しています。
外国人労働者の場合、試用期間中に、企業が期待していた日本語能力が不足していることがわかり、日本語能力の欠如を理由に本採用拒否をすることがあります。
本採用拒否は、採用決定時に知ることができず、また知ることが期待できないような事実を知るに至った場合に認められます。
企業は、日本語検定試験の成績、履歴書、採用面接等によって、日本語でどの程度のコミュニケーションを取れるかを判断できる機会があったので、採用決定後に期待していた日本語能力が不足しているとわかったとしても、容易に本採用拒否は認められません。
採用決定段階で、求める日本語能力の水準を明確にした上で、その水準を満たしているかを見極める必要があります。
自発的な退職、普通解雇、雇止め等による契約終了は、日本人労働者の場合と基本的に同様です。 普通解雇にあたり、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合にあたらないか(労働契約法16条)、雇止めにあたり、更新に合理的な期待があり、 更新拒絶が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合にあたらないか(労働契約法19条)が問題になります。
外国人労働者が離職する場合に、当該外国人労働者が再就職を希望するときは、関連企業等へのあっせん、教育訓練等の実施・受講あっせん、求人情報の提供等の援助を行うよう努めることが求められています(外国人雇用管理指針)。
急な退職・行方不明になるケース
外国人労働者は、働くためにわざわざ日本にやってきているので、給料アップやキャリアアップに対する期待が高い傾向があります。 外国人労働者に定着してもらい、離職を防止するためには、明確な賃金規程や、公平な人事評価制度が必要です。 また、外国人労働者の給料やキャリアに対する希望を把握するために、日常的にコミュニケーションをとり、定期的に面談することも効果的です。
外国人労働者が、突然、退職して行方不明になった場合、日本人労働者の場合と比べて、連絡を取るのが難しいことがあります。
長期間の無断欠勤は、普通解雇または懲戒解雇の理由があり、労働基準法の解雇手続を取る限り、解雇は有効ですが、行方不明になった労働者に対する解雇の意思表示が必要になります。
就業規則に、無断欠勤状態が自然退職事由になる(例えば「従業員が、原因の如何を問わず、会社に出勤しない状態又は会社に届け出た連絡先で会社と連絡不能となった状態が1か月以上継続した場合、従業員は自然退職とする。」)と定めていれば退職になりますが、
そのような定めがなければ、民法98条による「公示送達による意思表示」を裁判所に申し立てる必要があります。

5.技能実習生の場合
外国人労働者が技能実習生の場合、実習実施者である企業は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、技能実習を行わせる環境の整備に努めることが求められています(技能実習法5条1項)。
企業は、技能実習生ごとに技能実習計画を立て、外国人技能実習機構の認定を受けます(技能実習法8条)。そのため、企業は、技能実習法や技能実習計画との関係で、技能実習生が働き続けられるようにサポートする必要があります。
例えば、企業は、技能実習1号による在留期間満了までに技能実習2号への在留資格変更に必要な技能実習計画を作成して認定を受ける必要がありますが、この手続を怠って、技能実習生が在留資格の変更ができなかった場合、技能実習生に対して民法上の不法行為責任が生じます。
また、企業が技能実習計画と異なる業務を命じると、技能実習生に資格外活動をさせることになり、外国人労働者は罰則の対象とされてしまいます(入管法19条1項、73条)。 企業も、不法就労活動をさせたとして、処罰の対象となり得ます(入管法73条の2第1項1号)。 企業が、技能実習生に資格外活動を行わせることを内容とする業務命令をすれば、民法上の不法行為責任が生じます。
6.外国人労働トラブルを未然に防ぐためのポイント
このように、外国人労働者を雇用した場合の労働トラブルは、外国人労働者特有の在留資格、日本語能力不足、文化的背景の違いが大きな要因になっています。 これらの労働トラブルを防ぐためには、①在留資格の定期的なチェックと管理、②明確な就業規則と雇用契約の徹底、③多言語対応や「やさしい日本語」の活用が効果的です。
ポイント① 在留資格の定期的なチェックと管理
外国人労働者による就労の可否および就労が認められる範囲は、本人が持っている在留カード、パスポート(資格外活動許可証印シール)、資格外活動許可書によって確認できます。
採用時には、偽造コピーのおそれもあるので、原本を確認するべきです。
採用後も、外国人労働者が在留期間を超過して就労してしまわないように、企業も、外国人労働者の在留期間を管理する必要があります。
在留資格を定期的にチェックするといっても、企業が、旅券や在留カードの原本を管理するということではありません。 使用者が、労働契約にあたり、外国人労働者のパスポートを預かった事件がありましたが、裁判所は、「パスポートは、外国人が国外に出国するに当たって必要となる重要書類であり、その管理を第三者が行うことは外国人の出国の自由を制約するものである。 パスポートの管理については、所有者の自発的な自由意思に基づいて預かり、保管を開始することが必要であり、かつ、その場合であっても、所有者から返還を求めた場合には直ちに返還される必要があるというべきであって、返還に条件を付したり、 保管者の裁量に基づく許可制にしたりすることなどは、外国人の移動の自由を制限するものとして、公序良俗に反し、許されない。」と判断しました。

ポイント②明確な就業規則と雇用契約の徹底
労働条件に関わるトラブルは、多くの場合、雇用契約書や就業規則に、労働条件をきちんと明示していないことが原因で発生します。
雇用契約を締結するにあたり、雇用契約書に、賃金、労働時間、従事すべき業務の内容、契約期間等の基本的な労働条件がわかりやすく、一義的に記載されているかをチェックすべきです。
これに加えて、在留資格との関係で、在留資格に定められた就労の範囲と実際の業務内容が合致しているか、在留期間の満了時期を過ぎていないか、労働時間数が就労可能な時間数を超えていないか等の確認も必要です。

ポイント③多言語対応や「やさしい日本語」の活用
企業は、労働基準法の内容、就業規則を周知することが必要ですが(労働基準法106条)、外国人労働者に周知する際には、分かりやすい説明書や行政機関が作成している多言語対応の広報資料を用いる、母国語を用いて説明する等、
外国人労働者の理解を促進するため必要な配慮をするよう努めることが求められています(外国人雇用管理指針)。
また、企業は安全衛生教育を実施することが必要ですが(労働安全衛生法59条)、外国人労働者に対して実施する際には、
母国語を用いる、視聴覚教材を用いる等、当該外国人労働者がその内容を理解できる方法により行うことが求められています。
特に、外国人労働者に使用させる機械、原材料の危険性や取扱方法は、安全を確保するために、確実に理解されるよう留意が必要です。
このように、外国人労働者への説明・指導や研修は、日本語能力や文化的背景の違いを考慮して、十分に理解してもらえるように工夫する必要があります。
就業規則や業務マニュアルの母国語への翻訳も重要ですが、「やさしい日本語」の活用も効果的です。
「やさしい日本語」とは、難しい言葉を言い換えるなど、相手に配慮したわかりやすい日本語のことです。
簡潔な文章にする、言葉を易しくするなど、表現を工夫することで伝わりやすい日本語になります。出入国在留管理庁が、「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」を作成しており、参考になります。

LECのおすすめ研修 【日本人社員向け】外国人対応のためのわかりやすい日本語研修
7.トラブル発生時の解決方法と相談先
労働トラブルを回避するための予防策を講じても、残念ながら、労働トラブルが発生してしまう場合があります。労働トラブルが発生した場合は、速やかに職場環境の改善に取り組むとともに、自社だけで解決できない場合は行政機関や専門家に相談することも選択肢です。
職場環境改善(問題解決フローの整備と早期介入)
企業は、外国人労働者の苦情や相談を受け付ける窓口の設置等、体制を整備し、日本における生活上又は職業上の苦情・相談等に対応するよう努めることが求められています(外国人雇用管理指針)。
外国人労働者と労働トラブルが発生し、外国人労働者から苦情や相談があったときは、事実関係を迅速かつ正確に確認し、速やかに被害を受けた外国人労働者に対する配慮のための措置を行い、再発防止に向けた措置を講じます。
相談窓口担当者が、相談の内容や状況に応じ適切に対応できるように、あらかじめ、問題解決フローを整備しておくべきです。
行政機関・専門家への相談
厚生労働省の外国人雇用サービスセンターは、外国人を雇用する企業への雇用管理に関する支援をしています。出入国在留管理庁の外国人在留総合インフォメーションセンターは、入国手続や在留手続に関する相談に対応しています。
また、「外国人在留支援センター(通称:FRESC)」は、日本に在留する外国人の支援を行う関係機関が集まった施設であり、外国人を雇用する企業の一元的支援を行っています。労働基準法等の労働関係法令や労務管理、安全衛生管理に関する相談対応をしてもらえます。
在留資格に関してトラブルになったときは行政書士、労務管理に関してトラブルになったときは社会保険労務士・弁護士などの専門家に相談することが考えられます。外国人労働者との間で係争になり、民事訴訟、労働審判、労働局の紛争調整委員会によるあっせん等が開始した場合は、弁護士に相談して代理人になってもらうことが考えられます。
労働トラブルになる前の段階から専門家に相談し、予防策を講じることも効果的です。
8.まとめ:トラブルを回避して安全・安心な外国人雇用を実現するには
国籍及び社会的文化的背景を認め合い、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する多文化共生社会において、日本人労働者と外国人労働者が生き生きと働き、企業が発展していくためには、 上記のような労働トラブルを予防・解決するための仕組みを整えることも重要ですが、外国人労働者と日常的にコミュニケーションをとり、不安や疑問があったときにすぐに相談できる関係性を築いていくことも大事だと考えています。
LEC東京リーガルマインドのおすすめ研修
外国人材の雇用・育成を考えている方向け
- 外国人雇用管理主任者 認定講座
- 外国人採用スタートアップ研修
- 【日本人社員向け】外国人対応のためのわかりやすい日本語研修
- 外国人社員の労務管理研修(人事担当者向け)
- 外国人活躍推進研修(経営者・人事担当者向け)
- eラーニング 動画で学ぶ異文化コミュニケーション入門
日本語や日本特有の習慣を理解し活躍したい方向け
研修のラインナップ
講師派遣・オンライン外国人/グローバル人材研修
- 外国人採用スタートアップ研修
- 外国人社員 研修「日本語発音トレーニング」
- 外国人社員の労務管理研修(人事担当者向け)
- 外国人活躍推進研修(経営者・人事担当者向け)
- 外国人社員受け入れ対応研修
- グローバルマインドセット研修
- 外国人社員向けビジネスマナー研修
- 外国人社員向け日本の顧客対応研修
- カスタマーハラスメント研修(外国人向け英語対応可能)
- 海外赴任者向け研修
- 【外国人社員向け】ビジネス日本語研修
- 【日本人社員向け】外国人対応のためのわかりやすい日本語研修
- 外国人社員のビザ取得・入国手続き支援研修(経営者・人事担当者向け)
- インバウンド顧客対応研修
- 【採用担当者向け】外国人人材の採用を成功させる為の基本的な考え方
- 【管理職向け】外国人部下の力を伸ばすマネジメント術
- グローバルマーケットにおける競争戦略と市場調査研修
- グローバルビジネスリスクとリスクマネジメントの戦略研修
- グローバルマーケティング戦略と市場展開の戦略研修
- 国際交渉と契約のスキルの向上研修
- 国際的なビジネス戦略の立案と実行研修
- グローバル時代のリーダーシップコース研修
- 外国人材のためのグローバルリーダー育成研修
- 米国発!ダイバーシティマネジメントのための協働的リーダーシップ研修
- 【日本人社員向け】ビジネス現場ですぐ使える!”異文化理解研修”
- 【外国人社員向け】働きながら学ぶ日本語研修 基礎から実践へ(CEFR日本語版A1レベル、日本語能力試験N4-N5レベル対象)
- 【外国人社員向け】ビジネスですぐ使える日本語研修(CEFR日本語版B1-B2レベル、日本語能力試験N1-N2レベル対象)
- 外国人留学生の国内就職支援研修プログラム
eラーニング外国人/グローバル人材研修
試験対策研修
こちらもおすすめ【コラム記事】
監修者情報
友成 実(ともなり みのる)

| プロフィール | 広島大学法学部法学科を卒業後、司法研修所での研修を経て、第一中央法律事務所に入所し、現在に至ります。 約18年にわたり、弁護士として、様々な業種の企業の民事再生や私的整理などの事業再生案件に携わってきました。経営革新等支援機関として認定されています。 また、使用者・労働者双方の労働問題に積極的に取り組んでいます。東京弁護士会の労働法制特別委員会に所属し、社会保険労務士の登録もしています。 その他、企業の契約、訴訟、M&Aなど企業法務全般、個人の債務整理の業務にも従事しています。 |
|---|
まずはお問い合わせください!
LEC東京リーガルマインドは貴社の人材育成を成功させるため、集合研修・eラーニング研修・試験対策研修・ブレンディング研修まで、様々なプランをご用意しております。詳細資料のご請求やお見積りのご依頼は、お気軽に法人事業本部まで。
