- マネジメント
- 公開日:
管理職必見!
職場の信頼関係構築術|人材育成と組織力向上のコツ

「信頼できる上司のもとで働きたい」――それは多くの人が職場に求める本音ではないでしょうか。
近年、リモートワークや多様な働き方が進む一方で、組織内の“信頼の質”が問われる場面が増えています。部下のやる気が見えない、チームがまとまらない……そんな管理職のお悩みの背景には、「信頼関係の不在」が潜んでいることも少なくありません。
アドラー心理学では、人は「つながり」を感じられるときに本来の力を発揮できると考えます。
本コラムでは、アドラー心理学の専門家である筆者が、信頼関係の土台をどう築くか、そのために必要な視点やスキルを、実践例を交えて分かりやすくご紹介します。
職場の空気を変えるヒントを、ぜひ見つけていただけたら嬉しいです。
まずはお問い合わせください!
LEC東京リーガルマインドは貴社の人材育成を成功させるため、集合研修・eラーニング研修・試験対策研修・ブレンディング研修まで、様々なプランをご用意しております。詳細資料のご請求やお見積りのご依頼は、お気軽に法人事業本部まで。
目次
- 1.職場での人材マネジメントとは?
- 2.職場マネジメントに欠かせない「信頼関係」
- 3.信頼関係構築に必要なスキル・視点
- 3‐1.コミュニケーション力とアサーション
- 3‐2.チームビジョン・目標設定の方法
- 3‐3.心理的安全性の確保
- 3‐4.メンバーの成長促進とマネジメント
- 4.具体的な事例
- 事例1:指摘ばかりだった上司が変わったことで、部下が自走し始めた
- 事例2:チームの目標を“共に描く”ことで、離職の危機を乗り越えた
- 事例3:オンラインでも信頼は築ける――1on1の工夫で、離れていてもつながれる
- 5.まとめ
- LEC東京リーガルマインドのおすすめ研修
- ✓人材育成と組織力向上を目指す方向け
- ✓リーダーとしてのスキル向上を目指す方向け
- 研修のラインナップ
- こちらもおすすめ【コラム記事】
- 監修者情報
1.職場での人材マネジメントとは?
「最近の部下は何を考えているのか分からない」――研修先の管理職の方から、こんなお悩みを耳にすることがあります。かつてのように「背中を見て学べ」という指導が通じにくくなり、管理職自身がどう振る舞えばよいのか迷っている、そんな声も少なくありません。
職場における人材マネジメントとは、「人を育て、組織としての成果を上げていくプロセス」を指しますが、その土台にあるのは一人ひとりへの“関心”と“尊重”です。命令や管理ではなく、「どうすればこの人が力を発揮できるか」を共に考える姿勢が求められるようになっています。
アドラー心理学では、人は「貢献感」、すなわち“自分はこの場で役に立っている”という感覚を持つことで、前向きに行動し、成長していけると考えます。部下が主体的に動き、チームが自律的に機能していくためには、「一人の人として大切にされている」という実感が不可欠なのです。
また、マネジメントには、“信頼”という要素が欠かせません。職位による上下関係だけでは、人は動きません。日々の声かけ、1on1での対話、失敗への理解ある対応……こうした細やかな関わりを通じて、「この上司のもとでなら頑張りたい」と思える関係性が育まれていきます。
とはいえ、完璧なマネジャーである必要はありません。うまくいかないときも、迷いながらも、誠実に向き合おうとする姿勢こそが、チームに安心感をもたらします。自分も悩んだり困ったりしながら、それでも前に進んでいきたいのだ、だから皆の力を貸してほしい、こんな姿勢でいることがチームの結束力を高めることにもつながるのです。
マネジメントとは、難しさの中にもやりがいのある、人と人との営み。だからこそ、アプローチ次第で、職場の空気は大きく変わっていきます。
2.職場マネジメントに欠かせない「信頼関係」

「この会社を辞めようと思ったきっかけは、上司との関係でした」――人材定着に関する調査を見ても、離職理由の上位には、いつも“人間関係”が挙げられています。給与や仕事内容といった条件だけでは、長く働き続ける動機にはなりにくい時代。特に、日々の仕事を共にする上司との信頼関係は、部下にとって「この職場にいる意味」を左右するほど重要です。
信頼関係とは、「この人なら大丈夫」と思える“安心感”と、「自分の声が届いている」という“実感”の積み重ねから生まれます。たとえば、ちょっとした失敗にも過度に叱責されることなく、努力や挑戦を温かく見守ってもらえる環境では、人は安心して自分の力を出せるようになります。
アドラー心理学では、他者との関係性において、「相手を仲間として接する姿勢」が重要とされています。上司と部下という役割を超え、一人の人間として互いに尊重し合うことが、信頼を育む第一歩です。
たとえば、上司が、「あなたの意見を聞かせてほしい」と真正面から伝えるだけで、部下の姿勢が変わることがあります。自分に期待されている、自分の考えに価値があると感じられるとき、人は、“組織の一員”としての連帯感や責任感を持てるようになるのです。
また、「心理的安全性」という言葉も近年注目されています。これは、チームの中で「こんなことを言ったら否定されるのでは」「自分だけ浮いてしまうかも」といった不安がなく、安心して自分らしくいられる状態を指します。この心理的安全性が高いチームほど、率直な意見交換が活発になり、創造性や生産性も向上するという研究結果もあります。
裏を返せば、信頼関係が築けていない職場では、ミスを隠す、意見を言わない、学び合いが起こらない――という「見えない停滞」が起きてしまいます。チームの一体感が失われれば、やがては成果や業績にも影響を与えることになるでしょう。
信頼関係は、一朝一夕には生まれません。しかし、日々の関わり方や態度を変えることで、少しずつでも育てていくことができます。アドラー心理学の言葉を借りれば、「人はこの世界に居場所があり仲間がいるという実感があれば、勇気を持って前に進める」のです。
今の職場に、ほんの少しだけ“安心して話せる関係”が増えるだけで、働く人の気持ちや行動は確実に変わります。信頼関係の構築は、管理職が最も注力すべき「土台づくり」なのではないでしょうか。
3.信頼関係構築に必要なスキル・視点
3‐1.コミュニケーション力とアサーション

「伝えたつもりが伝わっていなかった」「つい強く言ってしまい、関係がぎくしゃくしてしまった」――職場での人間関係のもつれの多くは、実は“コミュニケーションのすれ違い”から生まれています。
人材マネジメントにおける信頼関係の土台は、やはり「日々のコミュニケーション」にあります。上司からの何気ない一言が、部下の勇気をくじくこともあれば、逆に一言が、「この人と働けて良かった」と思わせることもあります。
ここで注目したいのが、「アサーション」という考え方です。アサーションとは、自分の考えや気持ちを、相手を尊重しながら率直かつ誠実に伝えるコミュニケーションの方法です。言いたいことを我慢するのではなく、かといって感情的にぶつけるのでもなく、「私メッセージ」で冷静に伝えることが特徴です。
たとえば、部下の業務ミスに対して、「なんでこんなこともできないの?」と責めてしまえば、信頼関係はすぐに損なわれます。しかし、「この作業が間違っていたことで、全体のスケジュールに影響が出てしまったよ。次は、同じ失敗を繰り返さないためにも、一緒に確認して進めてほしい。」と伝えれば、相手も受け入れやすく、前向きな改善につながりやすくなります。
アドラー心理学では、「人は相手から信頼され、尊重されていると感じたとき、もっとも建設的に動く」と考えます。つまり、信頼されていると感じることで、その人自身が信頼に応えようという“勇気”を持てるようになるのです。
職場でのアサーティブな関わりを意識することで、相手も「ネガティブなことでも話して大丈夫なんだ」と感じ、自然と対話の質が深まっていきます。そして、その積み重ねが、信頼と安心感につながっていくのです。
もちろん、すぐに完璧なアサーションができる必要はありません。自分の伝え方を一つひとつ丁寧に見直し、相手の反応に耳を傾けること。その小さな姿勢が、職場の空気を変える第一歩になるのです。
3‐2. チームビジョン・目標設定の方法

「このチームは、どこに向かっているのかが分からない」――職場でのモチベーション低下の背景には、方向性の不明瞭さがあることも少なくありません。人は、目指す“意味”や“価値”が見えない中では、自分の力を発揮しにくくなるのです。
そこで重要になるのが、ビジョンと目標の共有です。管理職がリーダーとして果たすべき役割の一つは、「私たちは、どこに向かっているのか」を明確に言語化し、チーム全体で共有することです。
アドラー心理学では、「人は目的志向で行動する存在」とされます。過去の経験ではなく、“これからどうしたいか”に目を向けることで、人は自ら変化し、行動を選び取っていく力を持っています。だからこそ、組織の未来像や理想の姿を明確に描くことが、行動のエネルギーにつながります。
たとえば、「売上〇%アップ」や「ミスを減らす」といった数字目標も大切ですが、それだけでは心が動きにくいものです。それよりも、「お客様から“ありがとう”をもっともらえるチームになろう」「誰かが困ったときに自然と手が伸びる職場にしよう」といった“意味のある目標”が、人の内側から動機づけを生み出します。
そして、目標設定は「一方的に与えるもの」ではなく、「共に創るもの」として考えることが大切です。上司がすべてを決めて伝えるのではなく、メンバーと対話をしながら「何を目指すか」「どう進むか」を一緒に描いていく。そのプロセスそのものが、チームの一体感や信頼感を育んでいきます。
もちろん、一人ひとりのメンバーの価値観や強みにも配慮しながら、個別の役割や成長目標を設定することも重要です。「あなたのこの強みが、今のチームにとってとても大切だよ」と伝えるだけで、部下は自分の存在価値を実感し、前向きにチャレンジできるようになります。
目標は、ただ“達成する”ためのものではありません。共に働く仲間と「ここに向かいたい」という気持ちを確かめ合いながら、信頼を深めていく“道しるべ”なのです。
3‐3.心理的安全性の確保

「こんなこと言っても大丈夫かな」「間違ったらどうしよう」――職場でそう感じた経験は、誰しも一度はあるのではないでしょうか。こうした不安が続くと、人は自分を守るために沈黙を選び、本音を隠してしまいます。
このような状況を防ぐために、今あらためて注目されているのが「心理的安全性」です。
これは、チームの中で「失敗しても否定されない」「自分の意見を言っても大丈夫」と感じられる状態のこと。心理的安全性が高い職場では、メンバーが安心して発言や行動ができるため、学びや挑戦が促され、結果的に組織全体のパフォーマンスも向上していくのです。
アドラー心理学では、人が前向きに行動するためには「勇気」が必要だとされます。
この勇気は、「ここにいていいんだ」「自分には価値があるんだ」という安心感の中で、初めて湧き上がってくるものです。つまり、心理的安全性とは、部下が勇気を持って動ける“土壌”なのです。
では、心理的安全性を育むには、どうすればよいのでしょうか。
まず大切なのは、「否定しない姿勢」です。意見に賛成できないときも、すぐに「それは無理だよ」と切り捨てるのではなく、「なるほど、そういう視点もあるんだね」と一度受け止めてから話を進めることで、相手の心は開きやすくなります。
また、「見守る力」も欠かせません。失敗を責めるのではなく、「挑戦したこと」を認める関わりがあると、部下は、「次はもっと頑張ろう」と自ら立ち上がっていけるのです。
「ありがとう」「助かったよ」「よく気づいてくれたね」――こんな短い言葉にも、心理的安全性を育む力があります。職場において、上司からのちょっとした感謝や承認は、部下にとって想像以上に大きな励みになるのです。
心理的安全性は、特別な制度や取り組みが必要なものではありません。
日々のやりとりの中で、相手を信頼し、尊重する関わりを積み重ねること。それが、誰もが安心して意見を出し合える、風通しのよい職場づくりにつながっていくのです。
3‐4.メンバーの成長促進とマネジメント

「自分で考えて動いてほしい」「もっと主体的に仕事をしてほしい」――多くの管理職の方が抱える、共通の悩みではないでしょうか。けれど、部下が動かない背景には、「どうせ認められない」「失敗したら責められる」という無意識の不安があることも少なくありません。
人が本来の力を発揮するには、「成長したい」という内なる意欲を支える環境が欠かせません。アドラー心理学では、人は本来、“成長したい”“役に立ちたい”という前向きな力を持っていると考えます。その力を引き出すには、評価ではなく「勇気づけ」が必要です。
勇気づけとは、「あなたには力がある」「あなたの存在は大切だ」と伝える関わりです。
たとえば、成果が出たときだけでなく、たとえ状況が思わしくないときであったとしても、「粘り強く取り組んでいるね」「細かいところに気づいてくれて助かるよ」と、日々の努力や姿勢に目を向けて言葉をかけること。これが、部下にとって大きなエネルギーになります。
また、成長を促すマネジメントには、「任せてみる」ことも大切です。最初から完璧でなくて構いません。一定の裁量や責任を持たせることで、部下は「信頼されている」と感じ、自分の頭で考える力を伸ばしていけます。
さらに、1on1などの対話の中で、「どうしたいと思ってる?」「どんなふうに取り組んでみたい?」と問いかけることで、自ら目標を設定し、成長に向かう意識を高めていくことができます。
もちろん、うまくいかないときもあります。そのときは、「失敗したけど、挑戦したことがよかったね」と伝える。これも大事な勇気づけの一つです。ミスを責めるのではなく、次に生かすきっかけと捉える姿勢が、信頼関係を深めてくれます。
人は、誰かに“見守られている”と感じるとき、最も力を発揮します。
マネジメントとは、成果を管理することだけでなく、人の成長を支える営みでもあります。部下が、「自分はここで成長できている」と実感できる職場は、結果として組織全体の力を引き上げることにもつながっていくのです。
eラーニング「コミュニケーション能力で高める組織マネジメントを学ぶ」
の一部を無料でお試しいただけます。
4.具体的な事例
事例1:指摘ばかりだった上司が変わったことで、部下が自走し始めた
(製造業・40代男性マネージャー)
ある製造業の中堅社員研修で印象的だったのは、「部下が自分から動いてくれない」と悩んでいた管理職の男性でした。
彼は、自らの責任感の強さから、細かな部分まで厳しくチェックし、指摘するスタイルを取っていました。しかし、部下の反応はどこか受け身で、ミスを恐れて萎縮してしまっている様子でした。
研修では、アサーティブな伝え方(参照:3‐1.「アサーション」という考え方)や勇気づけの関わりについて学び、「否定せずにまず認める」「プロセスに目を向けて承認する」ということを実践してもらいました。
すると、「些細なことでも『ありがとう』と言うようになっただけで、部下の表情が変わってきたんです」と、本人の口から変化が語られるように。
1ヶ月後には、「最近、部下が自分から『こうしてみたい』と提案してくれるようになった」という報告がありました。信頼関係の芽は、上司の“変わろうとする姿勢”から育っていくことを実感させられる事例でした。
事例2:チームの目標を“共に描く”ことで、離職の危機を乗り越えた
(IT企業・30代女性リーダー)
IT企業のプロジェクトリーダーである女性は、メンバーとの関係に悩んでいました。納期や成果に追われる日々の中で、目標が「達成すること」ばかりになり、いつしかメンバーの顔色も曇りがちに。「もう辞めたい」という声も出てくるようになっていました。
研修では、“意味のある目標”をチームで描くワークを導入。彼女はその後、あえて業務の手を止め、メンバーと一緒に、「私達はどんなチームでありたいか?」を話し合う時間を設けました。
最初は戸惑っていたメンバーも、「自分たちで未来を決めていいんだ」という感覚を持ち始め、少しずつ発言が増えていきました。
結果、「お客様から“このチームに任せたい”と思われるようになろう」というビジョンが生まれ、プロジェクトの雰囲気も一変。半年後には、離職を考えていたメンバーも、「ここで頑張ってみたい」と気持ちを切り替えていたそうです。
事例3:オンラインでも信頼は築ける――1on1の工夫で、離れていてもつながれる(人材サービス業・50代マネージャー)
コロナ禍でテレワークが中心となり、「チームがバラバラになってしまった」と感じていたある人材サービス企業のマネージャーは、研修で「オンラインでも信頼関係は築ける」という話を半信半疑で聞いていました。
しかし、「1on1の時間を“仕事の確認”ではなく、“相手を知る時間”にしてみては」という提案を受け、週1回の1on1の中で、あえて仕事以外のこと――最近嬉しかったこと、困っていることなど――をゆっくり聞く時間を作るようにしたそうです。
数週間後、画面越しでも、メンバーが少しずつ笑顔を見せるように。ある日、メンバーの一人から、「こんなにちゃんと話を聞いてもらったの、初めてです」と感謝のメッセージが届きました。
「物理的な距離はあっても、心の距離は縮められるんだ」と、マネージャー自身のマネジメントへの自信も高まっていきました。
5.まとめ
信頼関係は、職場におけるすべての土台です。
どれほど優れた仕組みや制度が整っていても、人と人とのつながりが希薄では、組織の力は十分に発揮されません。逆に、心から信頼し合える関係が育まれているチームでは、困難な状況でも前を向いて進む力が生まれてきます。
今回のコラムでは、アドラー心理学の視点を交えながら、信頼関係の重要性とその築き方についてお伝えしてきました。
人は、「貢献できている」「認められている」と実感できたとき、自ら動き、成長し、周囲に良い影響を与える存在へと変わっていきます。その変化の出発点は、上司やマネジャーが“信じて関わる”という姿勢にあります。
もちろん、理想通りにはいかない日もありますし、試行錯誤の連続かもしれません。けれど、部下のことを思い、対話を重ね、よりよい関係を築こうとする姿そのものが、チームに安心感をもたらします。
アドラーは、「人は変われる」「関係性は築き直せる」と教えてくれます。
信頼関係は、特別な才能がなければできないものではなく、小さな行動や言葉の積み重ねによって、誰にでも育んでいけるものです。
今、目の前にいる部下やチームの仲間と、どんな関係を築いていきたいか――
その問いに向き合うことが、これからの管理職としての大切な一歩になるのではないでしょうか。
信頼のある職場には、笑顔と成長があります。
そして、それを育む力は、あなたの中にきっとあります。
LEC東京リーガルマインドのおすすめ研修
人材育成と組織力向上を目指す方向け
リーダーとしてのスキル向上を目指す方向け
研修のラインナップ
eラーニングマネジメント研修
- 従業員のための内部統制入門
- コーポレートガバナンス・コード
- コミュニケーションスキルを学ぶ
- コミュニケーション能力で高める組織マネジメントを学ぶ
- 事例で学ぶコーチング入門
- マネジメント・プロセスとは?
- モチベーションのコントロール法を学ぶ
- メンバーの育成方法を学ぶ
- 新入社員の教育法
- ストレスマネジメントとは?(初級)
- リーダーとしての利益思考の身につけ方
- プロジェクトマネジメントとは?
- リーダーシップとは?(初級)
- リーダーシップとは?(中級)
- リーダーシップの発揮法を学ぶ
- リーダーシップのノウハウを知る
- 目標管理制度が活きる、部下との対話法とは?
- 部下のストレス対策を学ぶ
- 効果的な部下の指導法を学ぶ
- 部下のモチベーションアップ術を学ぶ
- 部下・後輩の「叱り方&育て方」とは?(初級)
- 部下・後輩の「叱り方&育て方」とは?(中級)
- 部下・後輩の「叱り方&育て方」とは?(上級)
- 現場が活性化する情報化の推進法とは?
- ハラスメント
- 厳しい指導か?パワハラか?(指導とパワハラの境とは?)
- 業績アップのための目標管理制度のポイントを学ぶ
- メンタルヘルスのトラブル予防法とは?
- 人権デュー・デリジェンスの基礎知識
- 問題解決力を高める
- コミュニケーション能力で高める組織マネジメントを学ぶ
- ナレッジマネジメントのイロハを学ぶ
- 業績アップのための目標管理制度のポイントを学ぶ
- 動画で学ぶ異文化コミュニケーション入門
こちらもおすすめ【コラム記事】
監修者情報
金井 津美(かない つみ)
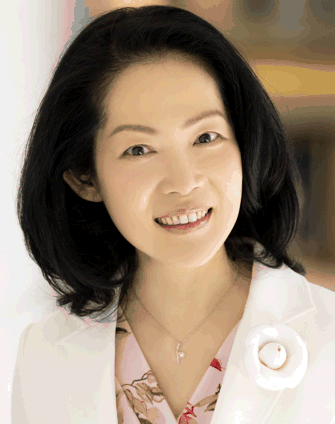
| プロフィール |
国家資格キャリアコンサルタント・キャリアコンサルティング技能士2級。
企業研修講師歴23年。アドラー心理学の実践歴25年を持ち、アドラー・コミュニケーション研究所プリンシパル、日本個人心理学会理事も務める。 ホテルオークラや国連日本政府代表部(NY)勤務などの社会経験を経て、2003年より講師として活動。JTB、日立製作所、三井住友銀行、アフラックなど多数の企業や官公庁で登壇。 アドラー心理学に基づいた「勇気づけ」の対話アプローチを活かし、信頼関係構築型のマネジメント研修に定評がある。「たのしく・わかりやすく・そしてあたたかく」を信条に日々登壇している。 |
|---|
まずはお問い合わせください!
LEC東京リーガルマインドは貴社の人材育成を成功させるため、集合研修・eラーニング研修・試験対策研修・ブレンディング研修まで、様々なプランをご用意しております。詳細資料のご請求やお見積りのご依頼は、お気軽に法人事業本部まで。
