- ビジネススキル
- 公開日:
AI時代だからこそ必要なロジカルシンキング(論理的思考力)とは?
最新トレンドや実践例をもとに分かりやすく解説!

ビジネスの現場では、日々様々な問題が発生しています。集客や売上の低下、クレーム対応、リソース不足などのやっかいな問題に対応することが求められる一方で、新規事業の立ち上げや、 新市場・新商品の開発等のビジネスサイクルのスピードがますます速くなっています。 そのような中で、生成AIが、ビジネスや生活領域に浸透し様々な課題解決に活用されてきていますが、生成AIを十分に活用していくためには、使う側の論理的思考能力、ロジカルシンキングの力が非常に重要であるということが指摘されています。 本コラムでは、AI時代におけるロジカルシンキングの必要性とメリット・実践例から、ビジネスの現場で、今すぐ活かせるロジカルシンキングのスキル強化策をご紹介していきます。
人材育成や社員研修でこんなお悩みはありませんか?
- 管理職が日々の業務に追われている
- 育成や戦略に時間を割けない
- 現場任せで指導の基準が定まらない
- 研修手法の選定にも迷いがある
- 最適な研修の選定に迷っている
本コラムでは、こうした課題に向き合うヒントとして、ロジカルシンキング(論理的思考力)の活用と、研修に活かせる具体的な展開方法をご紹介します。
\今すぐ確認したい方はこちらから/【無料体験】eラーニング「話し方・書き方が変わるロジカルシンキング」
目次
- 1.ロジカルシンキングとは<定義>
- なぜ今、ロジカルシンキングが必要なのか
- ロジカルシンキングで得られるメリット
- AI活用の時代に必要なロジカルシンキングとは
- 2.ロジカルシンキングに苦手意識のある方へ
- 3.ロジカルシンキング フレームワーク4選
- ロジックツリー(Logic Tree)
- MECE(ミーシー)
- ピラミッドストラクチャー
- 3C分析
- 4.ロジカルシンキング強化の3ステップとは
- 5.まとめ
- LEC東京リーガルマインドのおすすめ研修
- ✓eラーニングでロジカルシンキングを学びたい方には...
- ✓集合研修で取り入れたい企業様には...
- ✓AIやITのリテラシーを高めたい方には...
- ビジネススキル研修のラインナップ
- こちらもおすすめ【コラム記事】
- 監修者情報
1.ロジカルシンキングとは<定義>
はじめに、ロジカルシンキング(論理的思考)とは、具体的にどのような思考法を指すのかについて見ていきましょう。ロジカルシンキングとは、「物事を筋道立てて、矛盾なく一貫性をもって考える思考法」 で、ある結論にたどり着くまでに、事実・前提・根拠・理由を明確にしながら、飛躍や感情に流されずに整合性を保って考えることであるといえるでしょう。 例えば、ロジカルシンキングに沿ったプレゼンを行った場合、話者は根拠やデータをもとに、そうなった原因や理由を伝えることができ、聞く側に、導き出した結論とその根拠が明確につながっているという印象を与えます。 逆にロジカルでない思考法の場合、理由や根拠が直感や感情(何となくそう思った等)に頼ったものになり、話に一貫性がなく、ビジネス上では信頼性に欠けると判断されてしまうこともあるかもしれません。
なぜ今、ロジカルシンキングが必要なのか
インターネットやSNS、生成AIなどの進化・発展により、現代社会に生きる私たちは、日常的に膨大な情報にさらされています。しかし、情報の質はピンキリで、事実・意見・感情・誤情報が入り混じっています。 これらの膨大な情報をスピーディに活用しようとした場合情報の「取捨選択」や「信頼性評価」には、感情や直感だけでは限界があり、論理的に考えることで、「これは信頼できるのか?」「どんなバイアスがあるのか?」「根拠があるのか?」 といった判断ができるようになります。
ロジカルシンキングで得られるメリット
ここでは、ロジカルシンキングで得られるメリットを具体的に見ていきましょう。
- メリット① 説得力が増す
- 主張と根拠が筋道立っており、誰に対しても一貫性のある説明ができるので、説得力があり、プレゼンや商談のシーンで有力な武器になります。
- メリット② 問題解決力が高まる
- 感情や思い込みに流されず、事実ベースで問題を分解し、根本原因を突き止められるので、例えば売上が落ちたときなど、「雰囲気」ではなく、「客数」「単価」「リピート率」などの要因を切り分けて、打ち手を明確化できます。
- メリット③ 判断の質が上がる
- 複数の選択肢を比較し、長所・短所や影響を整理したうえで結論を導き出せるため、重要な意思決定に役立ちます。
- メリット④ 無駄な議論や誤解を減らせる
- 前提・用語・論点を整理したうえで話すため、相手とズレのない議論ができます。
会議でも、「何が問題なのか」「何を決めたいのか」を明確にしたうえで発言でき、脱線や感情的な対立を避けることができます。 - メリット⑤ 自分の考えに自信が持てる
- 自分の思考のプロセスを明確に説明できるため、他人の意見に流されにくくなります。そのため、反論された場合も、事実ベースの説明で冷静に対応できるようになります。

実際にeラーニング「話し方・書き方が変わるロジカルシンキング」を体験してみませんか?
AI活用の時代に必要なロジカルシンキングとは
昨今、ビジネスに浸透している生成AIについて、有効活用するために必要なスキルの1つとして、ロジカルシンキングが挙げられます。その理由として、
まず適切な問い(プロンプト)を設計できる能力が求められるという点にあります。
生成AIは、入力(プロンプト)の質が出力の質を決めるので、一連の思考プロセスを通じて的確な指示を生み出すことが肝心となります。
次にAIの出力を評価・分析する能力について、AIは“もっともらしい”だけで、必ずしも正しいとは限らないので、
出力内容を「前提」「因果関係」「事実との整合性」でチェックし、理由や根拠を検証した上で、最終的には人間の判断で補完・修正することが必要です。
上記のように、ロジカルシンキングを使うことで、AIを「道具」ではなく、「思考補助ツール」へと進化させ、人間が思考の設計図を作り、AIに部分的な分析・案出しを任せるという共創型の活用が可能になります。
2.ロジカルシンキングに苦手意識のある方へ
さて、ロジカルシンキング(論理的思考)というと、「自分には向いてないかも」、「理解できなさそう」などと思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、ロジカルシンキングの構成要素は、因果関係の把握や構造化など、「技術的な思考法」で成り立っているので、トレーニングによってそれらの技術を身に付け、向上させることができる思考法となります。つまり、ロジカルシンキングは、生まれつきの向き不向きというより、後天的なもので、適切な訓練によって習得できるものであるといえます。実際、MBAのカリキュラム等でも、ロジカルシンキングは学ぶものとして位置付けられています。
3.ロジカルシンキング フレームワーク4選
では、ロジカルシンキングで最もよく活用される思考のフレームワークについて、特にビジネスで有効な4つをご紹介していきます。
ロジックツリー(Logic Tree)
一つの問題を因数分解するように分解・展開していくツール。枝分かれ図を用いて視覚的に示すことで理解度が高まり、問題の構造を可視化できるので、「どこに原因があるのか」「何から着手すべきか」が明確になります。 主に、以下の2種類のロジックツリーが、ビジネスではよく使われます。
| 問題解決ツリー | 「なぜ起きたのか?」を深掘り(原因分析) |
|---|---|
| 目的達成ツリー | 「どうすれば達成できるか?」を展開(打ち手立案) |
◆活用例:
売上減少 → 客数減?単価減? → 客数減の原因は?広告?店舗?…というように因果関係を掘り下げていく。
MECE(ミーシー)
Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive(相互に重複せず、全体として漏れがない)が示す通り、問題を解決する際に、漏れなくだぶりなく思考できているかを見るツール。
特に複雑に、相互に関係しあう事例に対して、
情報・要素を重複なく、漏れなく分類・整理できているかを検証・判断することができます。
◆活用例:
新規事業のリスク分析を「市場」「競合」「社内資源」などに分類し、重複・漏れのないリストを作る/プレゼンの構成要素を、「費用」「効果」「実行リスク」に分けて話す。
ピラミッドストラクチャー
結論 → 根拠・理由 → 具体例の順に示す三層構造(ピラミッド型の論理展開)を基本とし、聞き手に分かりやすく論理的に説明することができるフレームワークです。 上司や顧客への説明・報告・提案で、「要するにどういうこと?」を先に伝えるスタイルといってもよいでしょう。
◆活用例:
①結論(例:新システムを導入すべき) → ②理由(例:費用対効果が高い、社内リソースで対応可能 )→ ③詳細データ(コスト予測、効果検証データ、社内アンケート)で構成する報告資料。
3C分析
Customer(市場・顧客)・Competitor(競合)・Company(自社)の3つの視点で環境分析を行うフレームワークです。市場環境を多面的に整理し、戦略立案のベースを構築することができます。
◆活用例:
新商品を出す際、「顧客のニーズ」「競合の状況」「自社の強み・弱み」を洗い出し、ポジショニングを決定。
eラーニング「誰でも身につく問題解決力」の学習内容や特徴を詳しくご覧いただけます。
社内での導入検討にも便利な、無料で一部を体験できるトライアルもご用意しています。
4.ロジカルシンキング強化の3ステップとは
先述したとおり、ロジカルシンキングは後天的な能力であるため、技術的なトレーニングによりスキルを高めていけるものとなっています。ここでは、ロジカルシンキングを強化するための具体的な手法を、【整理する⇒考える⇒伝える】という3つのステップに分けて、訓練法とともにご紹介します。
ステップ① 整理する
多くの種類の異なる情報を整理する力を鍛え、情報を構造化してとらえる習慣をつけていくと、複雑な事象でも全体像を把握しやすくなり、頭の中をクリアに保つことができます。
- 主な訓練内容:
- MECE(漏れなく・重複なく)で分類する練習
- ロジックツリーを使って物事を分解する練習
- 5W1Hや因数分解で要素を見える化
例:「定番商品の売上が下がっている」の原因を、「新規客数」「リピート客数」「購入数」「購入単価」「購入頻度」に分解 → それぞれの要因をデータで確認する。
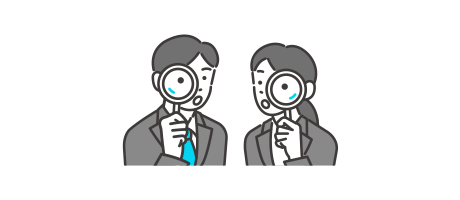
ステップ② 考える
筋道を立てて結論を出せるよう考えるステップで、「なぜこうなった?」「だからどうする?」を筋道立てて考えていき、因果関係、演繹・帰納法などを用いて思考し、チャート等にまとめ可視化できるようにします。
- 主な訓練内容:
- なぜなぜ分析(Whyを5回繰り返す)で理由を考え、まとめる練習
- ピラミッドストラクチャー(結論 → 根拠 → 事例)を練習
- 自分の主張を因果関係で裏づける訓練
例:結論「この施策は延期すべき」→ 理由① 法規制変更が確定していない、理由② 顧客への影響が大きい。

ステップ③伝える
他人に理解・共感してもらうために「伝える力」を鍛え、論理的に説明・説得することで相手に納得感を持たせ、相手の行動や態度変容を促していきます。図やフレームワークを使って、 伝えたいことを分かりやすく「見える化」する技術も必要になってきます。伝える力は、周囲からのフィードバックを得ることでより高めることができるので、積極的にプレゼンや提案を行い、継続的に学び続けることが大切になってきます。
- 主な訓練内容:
- プレゼンやメールで結論から伝える練習(PREP法など)
- 論点を整理し、論理の飛躍がないように話す訓練
- ピラミッドストラクチャーで図式化された資料の作成
- 伝えたいことをシンプルにまとめた無駄のない資料作成の技術
例:会議で「この2案を比較しました。A案を推す理由はコストと実行性です」と先に結論を伝え、その後に根拠を説明(資料の構成も同様に、結論から提示)する。

貴社に最適な人材育成方法、見つかります!
LEC東京リーガルマインドは集合研修・eラーニング研修・試験対策研修・ブレンディング研修まで、様々なプランをご用意しております。詳細資料のご請求やお見積りのご依頼は、お気軽に法人事業本部まで。
5.まとめ
ここまでで、ロジカルシンキングを強化する3ステップについてお伝えしましたが、様々なフレームワークなども、実際に自分でやってみないと活用イメージが湧きにくく、結局習慣化されないままになってしまうこともあるでしょう。 そうならないためにも、まずは研修やワークショップなどを受講することで、ロジカルシンキングにおける基礎的なトレーニングを一通り体験し、ビジネスの現場で常に使える習慣を身に付けることが大変重要です。
特にAI活用が浸透してきている現代においては、論理的な思考力をもって生成AIを活用する、という意識を持つことにより、AIは単なるツールではなく「思考を加速させるパートナー」となってくれます。 ロジカルシンキングに基づいたプロンプト(指示)が制作でき、AIを最大限に活用できる人材が、今後、企業にとって、大きな優位性をもたらすと言っても過言ではないでしょう。
LEC東京リーガルマインドのおすすめ研修
eラーニングでロジカルシンキングを学びたい方には...
集合研修で取り入れたい企業様には...
AIやITのリテラシーを高めたい方には...
ビジネススキル研修のラインナップ
eラーニングビジネススキル研修
- ビジネスマナーを学ぶ
- 成果主義のための仕事の整理整頓法
- 問題解決力を高める
- ビジネス文書の書き方
- クレーム対応で企業力UPを目指す
- 光る企画書の書き方
- 話し方・書き方が変わるロジカルシンキング
- 誰でも身につく問題解決力
- 今さら聞けない!「営業職のイロハとは?」
- 30分で学ぶコンプライアンス
- 従業員のためのコンプライアンス
- 顧客データ管理法を学ぶ
- 教えて、営業部長!ビジネス法の基礎
- 教えて、営業部長!下請業者との取引
- 営業担当者のための請負契約書作成術
- 営業担当者のための売買契約書作成術
- 営業担当者のための典型契約契約書の作成術
- 営業担当者のための非典型契約契約書の作成術
- 教えて、営業部長!債権回収のポイント
- 情報セキュリティ
- SDGs入門研修
- 業績アップに活かす財務諸表の見方
- コミュニケーションスキルを学ぶ
- 交渉力を高める(初級)
- 交渉力を高める(中級)
- ポジティブシンキングとは?(初級)
- ポジティブシンキングとは?(中級)
- ポジティブシンキングとは?(上級)
- マネジメント・プロセスとは?
- モチベーションのコントロール法を学ぶ
- リーダーとしての利益思考の身につけ方
- プロジェクトマネジメントとは?
- リーダーシップの発揮法を学ぶ
- ハラスメント
- ナレッジマネジメントのイロハを学ぶ
- プレゼンテーション力養成講座
- SWOT分析の活用法を知る
- ゲーム理論とは?Ⅰ
- ゲーム理論とは?Ⅱ
- マーケティングとは?(入門)
- マーケティングとは?(初級)
- マーケティングとは?(中級)
- 顧客とのパートナーシップの考え方を学ぶ(初級)
- 【外国人向け】日本で働くためのビジネス基礎研修(日本語)
- 【外国人向け】日本で働くためのビジネス基礎研修(ベトナム語)
- 動画で学ぶ異文化コミュニケーション入門
- eラーニングで学ぶ 不動産実務・業界講座
こちらもおすすめ【コラム記事】
監修者情報
志野 こと葉(しの ことは)
| プロフィール | コンサルティング企業や大手教育系企業にて25年にわたり商品開発・マーケティング・広報業務などに携わる。 特にWeb開発やデジタルマーケティング領域の業務を数多く経験。マネジメント職を経験後、産業カウンセラー、ハラスメント相談員等の資格を取得。 その後、公務員に転向し、企業の雇用問題や採用、人材育成、働き方等におけるさまざまな課題解決に携わる。 働く人に向けた幅広いテーマでビジネスコラムの執筆を行っている。 |
|---|
まずはお問い合わせください!
LEC東京リーガルマインドは貴社の人材育成を成功させるため、集合研修・eラーニング研修・試験対策研修・ブレンディング研修まで、様々なプランをご用意しております。詳細資料のご請求やお見積りのご依頼は、お気軽に法人事業本部まで。
