- 経営・企画
- 公開日:
製造業に求められるCX(コーポレート・トランスフォーメーション)とは?

長年、ものづくり大国としての地位を築いてきた日本。技術革新を重ね、高性能・高品質な製品を作り出す技術力で、日本製品は世界のあらゆる国々に輸出され利用されています。一方で、人件費・原材料の高騰、設備や機械、システムの老朽化、デジタル化の遅れなど、日本の製造業をとりまく環境には様々な課題が顕在化してきています。そんな中で今、日本の製造業に求められているCX(コーポレート・トランスフォーメーション)について考察します。
製造業が直面している課題
2024年5月に発表された経済産業省「製造業をめぐる現状と課題」(製造産業局発行)
によると、日本の製造業企業の過去25年間の売上高は400兆円程度でほぼ横ばいという状態を維持しています。その内訳をみてみると、国内市場は成熟化・縮小化が進んでいるのに対し、海外へ進出する日本の製造業者が右肩上がりで増えています。国内主要製造業500社の2022年のデータでは、海外売上比率はこの25年間で31%から53%と伸びており、現在は過半数の売上を国外で稼いでいることになります。この傾向は今後も続くと予想され、特に成長著しい新興国市場などにおいて日本の高品質・高機能な製品が求められており、輸出国や地域は今後も拡大していく見通しです。しかし一方で、海外売上比率の増加に反して、利益率が低迷するという課題が浮き彫りになってきました。せっかく製品が売れても、企業の利益に結び付かず、さらに市場が多角化すればするほど低利益性を招いてしまうという現状が指摘されています。
これらの課題に対し、グローバルビジネス展開に対応できるよう、従来の経営モデルを変化させるべきという考え方があります。これは、たとえ現時点では国内マーケットをメインに商品を提供している製造業企業であっても、今後の海外進出や、国内の競合対策(グルーバル企業の参入など)に備え準備を進めておく必要があるでしょう。
日本的経営とワールドクラスのギャップ
2024年5月に発表された経済産業省「製造業をめぐる現状と課題」(製造産業局発行)
によると、日本的経営とワールドクラスのギャップとして、経営手法や人材マネジメント等に関する数多くの項目が挙げられていますが、その中の主なものとして以下のような観点があります。
①組織構造
日本的経営では親会社・子会社・関連会社など個社を積み上げるエンティティベースの構造。個社や事業部ごとの部分最適を優先するため、機能面や人材面で重複・非効率が生じやすい。ワールドクラス経営ではグローバルで一つの会社と考え、親会社、子会社、支店等すべてを含む事業体をワンカンパニーとしてとらえ、その中で全体最適を追求します。
②採用・育成
日本的経営では、長期安定雇用を前提とした新卒や若手採用に比重をかけており、育成も、その後のOJTを中心とした社内技能教育なのに対し、ワールドクラスの経営では、重要なポジションを特定しスキルや能力を明確化し、そこに合う人材を採用している。純血主義に陥らないために外部からふさわしい人材の招聘やジョブローテーションを積極的に行っています。
③コミュニケーション
日本的経営では、日本人・男性中心という同質的なメンバー構成による「あうんの呼吸」による意思疎通が多く、明確なプロセスがなくても場当たり的な対応が通ってしまう現状があり、それが情報システムやデータベースの整備遅延につながっているという指摘もあります。一方、ワールドクラス経営では、国籍、人種、宗教など多種多様なメンバーが意思疎通するために、役割、権限、責任の定義を明確にし、プロセスの標準化や評価の透明性、データベース可視化、全てのメンバーが利用できる社内システムの整備等が進んでいます。
なぜ「技術で勝ってビジネスで負ける」のか?
半導体、液晶パネル、カーナビなどいずれも製品開発力・技術力では日本企業がリードしていたものの、製造、販売、マーケティング等で海外企業が優勢になるという状況が繰り返されています。エレクトロニクスを中心とした様々な製品市場で、日本企業は「技術で勝ってビジネスで負ける」と言われることがあります。このような状況を克服するにはどんな変革を行っていく必要があるのでしょうか。
経済産業省・厚生労働省・文部科学省が共同で毎年発行している「ものづくり白書」2024年版によると、
この問題を解決に導くために日本の製造業には、2つの変革が必要であるとされ、その2つとは、①強い経営組織への変革、CX(コーポレート・トランスフォーメーション)と、②デジタル技術による変革、DX(デジタル・トランスフォーメーション)であると説いています。このコラムでは特に①のCXについてご案内していきます。
CX(コーポレート・トランスフォーメーション)とは?
これまでの日本的経営の組織の中で、日本人同士の「あうんの呼吸」で意思決定がなされることが有効に機能していた時代もあったといえますが、時は変わり、グローバル競争の中で、経営の複雑性がますます高まっていることで、経営戦略や意思決定、ルールや権限、レポートライン、プロセス設計などの組織横断的な仕組みを言語化し、組織内に横ぐしで周知・定着させる必要がでてきました。国内・国外の事業所、支店などすべての拠点を一つの企業グループとして一体的な経営を行い、ヒト・モノ・カネ・データのリソースを可視化し最適に再配分するしくみを整えることが、強い組織づくりにつながるといえます。
CXとは、日本語では企業変革を意味します。従来の日本型の企業経営システムそのもの、いわばOS(コンピュータに必要不可欠な基本ソフトウェア)の抜本的なアップデートが求められていると言えます。
2024年6月に発表された経済産業省「グローバル競争力強化に向けたCX研究会」によると、CXの必要性を次のように述べています。
「グローバル競争時代における製造業の競争力の強化には、“現場力の高さ”に “強いコーポレート”が組み合わさり、両輪で組織が駆動する必要がある。不確実性の高い市場環境においてもイノベーションを起こし、稼ぐ力を高めていくためには、ビジネスモデルとビジネスプロセスを継続的に刷新(BX)し続けなければならない。その背骨となるのがコーポレート(CX)であり、そのツールとしてのデジタル(DX)である。」
CXを進めるために必要なこととは?
CX(コーポレート・トランスフォーメーション)は、組織全体の在り方を改革するものであるため、何よりもまずトップダウンの強い決断と意志表明が前提となります。そこでは、企業の存在理由や価値観・信条を明確にし、他社との違いや自社の優位性、将来にわたって大切にしたいこと・守りたいことを明確にしていくべきでしょう。
その後、イノベーションを起こすリーダー陣の強いリーダーシップにより、改革を進めていくことになります。これまでは見なかったことにして済ませてきた、いわゆる組織の膿を出しきるような局面もあるかもしれません。
CXを進める上で、どのような人材が求められるのでしょうか。
①巻き込み力と伝える力

企業の成長に向けた組織改革の大きなかじ取りは、相当な労力が必要です。このような改革を推し進められるのは「一握りのカリスマ性のある人物に限られるのでは?」と思われがちですが、それだけではありません。CXを実際に実行していくのは、社員、スタッフ一人ひとりなのです。皆が変化に合わせて正しく動けるように、道を示し、案内し、導いてくれる伴走型の現場リーダーが必ず必要となります。時には変革を拒む動きも起こってくるかもしれませんが、そのような時に、周囲の話をよく聞き、なぜ変革が必要なのかを的確に伝え、納得させ、周囲をどんどん「巻き込む力」が必要になります。周りからの信頼はもちろんですが、「伝える力」の高さが求められる役割であるといえるでしょう。
②ゼロベース思考とねばり強くやり抜く力
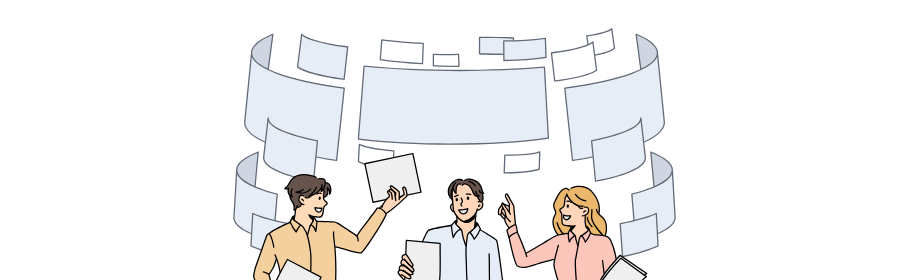
自社の組織にとって有効な変革とは何か、を考える際に、CXの原点ともいえるワンカンパニーであることを出発点にものごとを考えることがまずは求められます。これまで個社や事業所、地域や支店ごとに個別に決められていたルールや規則、条件を取り払って、ゼロベースで思考できるかどうかがカギとなります。カイゼンを繰り返したり、過去の実績を積み上げるのではなく、ゼロに戻してイチから考えます。新しい価値を産み、育てる労力を惜しまない人材が求められるでしょう。困難な問題が多くなることが予想されますが、ねばり強く対処し、最適解が出るまでやり抜く力のある人材が求められます。
③新技術、デジタル分野に強い人材
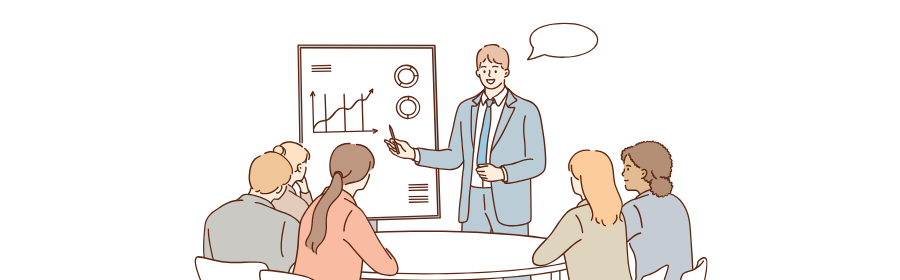
製造業企業におけるCXの効果を高めるために、DX(デジタル・トランスフォーメーション)を取り入れることは必要不可欠であるといえます。現在、国内製造業者の約80%が何らかのデジタル技術を活用しており、5年前の調査では約50%であったのに対し、大きく伸びているといえます(2024年度「ものづくり白書」より)。製造機能のみならず、DXで、物流や販売、顧客管理システムの刷新・拡充を行ったり、人事評価システム、タレントマネジメント等の新システムを導入・活用している企業は成長のスピードも速くなっています。業務効率化・最適化のための近道として、DXは1つの解となりうるでしょう。そのため、昨今のデジタル市場、デジタル技術についてよく学び、よく理解し、自律的にDXを推し進められる人材が必要となります。新しいシステムを採用する際にも、すべて業者まかせにせず自分たちでシステムの是非を判断できる最低限のITリテラシーが求められるといえるでしょう。
こちらもおすすめ【コラム記事】
LEC東京リーガルマインドのおすすめ研修
経営層・リーダー向け研修なら
企画立案・戦略立案・ゼロベース思考を鍛える研修なら
ITリテラシーを高めるには
研修のラインナップ
eラーニング経営・企画研修
- CSR(企業の社会的責任)入門
- 事例で学ぶコーチング入門
- SWOT分析の活用法を知る
- あなたがやらねばならない内部統制の知識
- やさしい内部統制の基礎
- リスクマネジメントとは?(初級)
- リスクマネジメントとは?(中級)
- 内部統制における評価と報告を学ぶ
- 部下・後輩の「叱り方&育て方」とは?(中級)
- 管理者・リーダー必須の経営分析のイロハを学ぶ
- 財務分析の手法
- インサイダー取引とは何か
- 今さら聞けない!「内部統制とは?」
- 情報セキュリティ
- Essential会社法
- Advanced 会社法
- Essential 環境法
- Advanced 環境法
- 何が不当表示に当たるのか?
- 入門・不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)
- Advanced 製造物責任法
- 知的財産権とは何か?
- 著作権法とは?
- Advanced独占禁止法
- 人権デュー・デリジェンスの基礎知識
- 従業員のための内部統制入門
- SDGs入門研修
- 会社のしくみを知る
- 人権デュー・デリジェンスの基礎知識
まずはお問い合わせください!
LEC東京リーガルマインドは貴社の人材育成を成功させるため、集合研修・eラーニング研修・試験対策研修・ブレンディング研修まで、様々なプランをご用意しております。詳細資料のご請求やお見積りのご依頼は、お気軽に法人事業本部まで。
監修者情報
反町 雄彦 そりまち かつひこ
株式会社東京リーガルマインド 代表取締役社長/弁護士
| 1976年 | 東京都生まれ | |
|---|---|---|
| 1998年 | 11月 | 東京大学法学部在学中に司法試験合格。 |
| 1999年 | 3月 | 東京大学法学部卒業。 |
| 4月 | 株式会社東京リーガルマインド入社、以後5年間、司法試験対策講座の講義を行い、初学者向けの入門講座から中上級向けの講座まで幅広く担当し、多くの短期合格者を輩出した。 |
|
| 2004年 | 3月 | 司法研修所入所。 |
| 2005年 | 10月 | 弁護士登録(東京弁護士会所属)。 |
| 2006年 | 6月 | 株式会社東京リーガルマインド取締役。 |
| 2008年 | LEC司法試験対策講座統括プロデューサーを務め、以後、現在に至るまで資格試験全般についてクオリティの高い教材開発に取り組んでいるほか、キャリアデザインの観点から、多くの講演会を実施している。 |
|
| 2009年 | 2月 | 同専務取締役。 |
| 2011年 | 5月 | 同取締役。 |
| 2014年 | 4月 | 同代表取締役社長。 |
| 2019年 | 4月 | LEC会計大学院学長 |
| 2023年 | 東京商工会議所中野支部・情報分科会長に就任 | |
| 2024年 | 一般社団法人ラーニングイノベーションコンソシアムの理事に就任 |

